※このページはプロモーションを含みます

この記事は5分で読めます
積立投資の利益が非課税になる「つみたてNISA(積立NISA)」。お得に資産運用でき、投資初心者にも使いやすい制度と言われていますが、なかにはつみたてNISAに向いていない人がいることも事実です。
今回はつみたてNISAをやめたほうがいい人、つみたてNISAをおすすめしたい人、それぞれの特徴をご紹介します。つみたてNISAに興味を持っている人は、自分はどちらのタイプに当てはまるか確認したうえで始めることを検討してみてくださいね。
目次
つみたてNISAという言葉はよく耳にするけれど、どのような制度かよくわからない人もいるでしょう。ここではつみたてNISAの仕組みや特徴とともに、メリットとデメリットをご紹介します。
つみたてNISAの最も大きなメリットは「最大20年間運用益が非課税になる」ことです。通常は投資の利益に対して20%程度の税金がかかりますが、つみたてNISAではこの負担がかかりません。
非課税となる対象は年間40万円までです(月額最大で3万3333円を積み立て)。たとえば毎年40万円積み立てて20年後に300万円の利益が出た場合、本来課税されてしまう約60万円をまるまる手元に残せるのです。
もちろん利益を確定させる(積み立てた商品を売る)のを20年後まで待つ必要はありません。20年の非課税期間のどこかで売ればいいので、余裕をもって売るタイミングを見極められます。
つみたてNISAは初心者でも利用しやすいよう、リスクやコストが低い商品に限定されています。具体的には金融庁が認めた投資信託(上場投資信託を含む)が対象です。そのため多くの商品から投資対象を選びたい人には物足りないかもしれません。
逆に商品が厳選されているということは、初心者でも選びやすいというメリットでもあります。どの商品を選べばよいかわからない人にとっては安心して利用できるのではないでしょうか。
つみたてNISAの特徴やメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください。
合わせてこちらもチェック!
お得なつみたてNISAでも、利用するのをやめたほうがいい人はいます。特に以下のような人はつみたてNISAをおすすめできません。
①すぐにお金を増やせると思っている人
②お金に余裕がない人
③がまんができない人
④老後資金を準備したい人
それぞれの特徴について詳しく解説していきます。
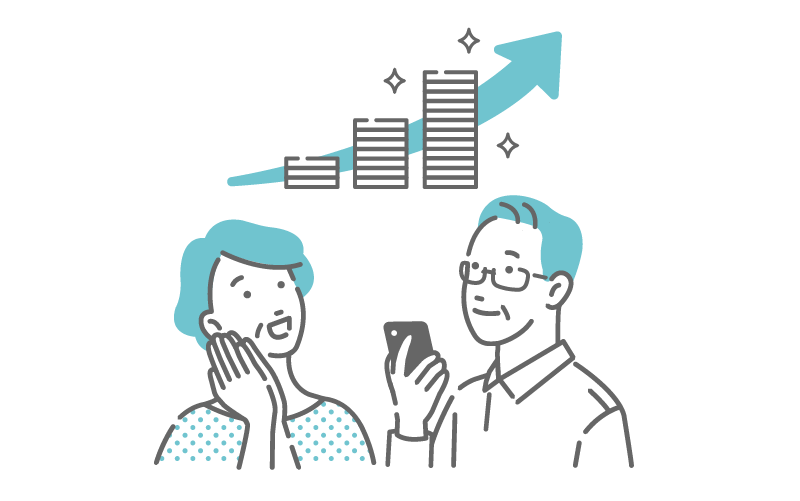
つみたてNISAは長期の積立投資を支援するための制度です。初心者でも安定的に運用しやすいよう、リスクやコストの低いインデックスファンド(株価指数などに連動する運用を目指す投資信託)を中心とした投資信託に限られています。
そもそも大きな利益を狙いやすい商品は損をする可能性も高いため、つみたてNISAの対象ではないのです。そのため短期的に大きな利益を狙いたい人はやめたほうがいいでしょう。
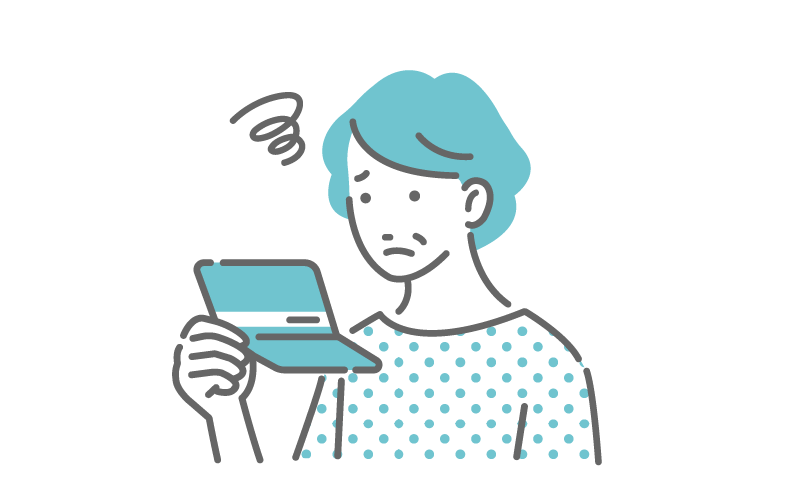
つみたてNISAは少額から始められる制度ですが、十分な蓄え(貯蓄)がない状態で始めるのはおすすめできません。
資産運用にはリスクがつきもので、つみたてNISAといえど損をする可能性は0ではないのです。そのため余剰資金(なくても当面の生活に困らないお金)で始めることが大切です。
つみたてNISAを始める目安として、生活費の半年分から1年分程度の貯蓄は確保しておくとよいでしょう。災害や新型コロナウイルスのような不測の事態はいつ起きても不思議ではありません。このような緊急時用の資金は預金として持っておくのが安心です。
つみたてNISAは緊急時用の資金には向いていません。いつでも引き出せると言われているものの、現金化するのに1週間程度はかかります。さらに引き出したいタイミングで値下がりしている可能性もあるためです。
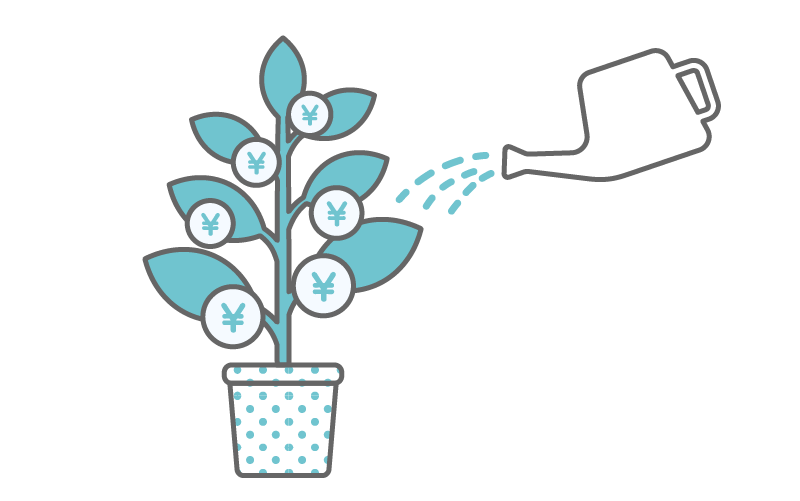
つみたてNISAの積立期間は最長20年間と長期にわたります。投資信託の価格は常に変動するので、利益が出るときもあれば損(元本割れ)をするときもあります。一時の値動きに踊らされてすぐに売ってしまったり、ほかの商品に乗り換えたりしてはつみたてNISAのメリットは半減してしまいます。
大切なのは長期的な視点を持ってコツコツ積み立てることです。「〇〇万円貯まったら売る」というように目標を立てておくと、一時的な値動きにも惑わされにくいのでおすすめです。
つみたてNISAは大きな損失が出にくいように作られた制度です。同じ金額を定期的に積み立てることで、投資信託の価格が下がっているときは多く買い、上がっているときは少なく買います。この投資手法を「ドルコスト平均法」といい、購入価格を平均化する効果があるため投資のリスクを抑えられます。
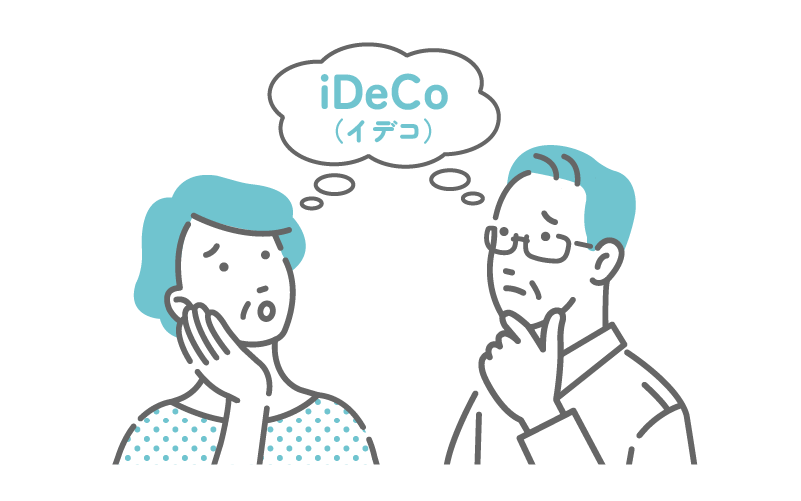
つみたてNISAは住宅購入資金や教育費などさまざまな目的で利用できる制度です。ただし現役世代(20~50代)で老後資金を準備したいなら、iDeCo(イデコ)の利用も視野に入れましょう。
iDeCoは老後のための資金形成に特化した制度です。原則60歳まで引き出せないため、老後資金を確実に準備したい人に適しています。さらに掛金が全額所得控除の対象となるため、つみたてNISA以上に高い節税効果が期待できます。
たとえば年収500万円の会社員がiDeCoで年間24万円を30年間積み立てた場合、合計140万円以上節税できます。ただし、iDeCoには加入条件があるので、iDeCoの公式サイトや勤務先に問い合わせて加入できるか事前に確認しましょう。
またiDeCoの最低掛金が月額5000円である点も注意が必要です。長期的に最低掛金を払い続けられないようなら、1回あたり最低100円から投資できるつみたてNISAで運用を始めるというのも一案です。
合わせてこちらもチェック!
逆に、つみたてNISAに向いているのはどんな人でしょうか?以下はつみたてNISAを始めることをおすすめしたい人の特徴です。
①余剰資金があり、長期的な視野を持って資産運用を始めたい人
②将来に向けてまとまった資産を準備したい人
③老後資金を貯めたい50代後半~60代の人
それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
余剰資金で長期的に資産運用できる人ならつみたてNISAはおすすめです。10年~20年のスパンで計画的に資金を準備したい人に向いています。長く運用することで複利効果(利益が利益を生む効果)が生まれ、最終的に大きな利益を狙いやすくなります。
また前述したとおり、一時的に損失が出ても慌てて売らずに腰を据えて運用することが大切です。たとえば新型コロナウイルスの影響で大きく値を下げた投資信託が1年足らずで値を戻した例もあります。長い視野で見て利益が出ているかどうかを判断しましょう。
つみたてNISAは老後資金より、子どもの教育資金やマイホーム資金など、20年以内に訪れる比較的近い未来の資金を準備するのに向いています。つみたてNISAはライフスタイルに応じて必要なタイミングで現金化しやすいというメリットがあります。
積み立てるお金の使い道が決まっている場合は、目標金額を立てておくことをおすすめします。目標金額に達していれば、それ以上儲けようとして売るタイミングを逃すことを回避できるためです。
老後資金の準備にはiDeCo(イデコ)が適していると解説しましたが、現時点でiDeCoは60歳未満の人しか加入できません。法改正により2022年5月からは65歳未満まで加入できるようになったものの、対象は60歳以降も国民年金に加入している人に限定されます。
60代に近い人であれば年齢制限のないつみたてNISAのほうが長い期間積み立てられますし、60歳以上でiDeCoに加入できない人も利用できます。iDeCoの積立期間が短くなる人やiDeCoに加入できない人はつみたてNISAで老後資金の準備をおこなうとよいでしょう。
このパターンならつみたてNISAが良い、これならiDeCoの方が…と言われると「結局、自分はどの制度で資産運用を始めたら良いかわからない!」という人もいるでしょう。
そんな時は資産運用のプロに相談してみるのも一案です。中でも、IFA(独立系の資産運用アドバイザー)に相談すると、顧客本位の中立的なアドバイスが期待できます。最適な資産運用を提案してくれるかもしれません。
自分に合った相談相手を見つけることも難しいものですが、「資産運用の無料相談窓口」なら、専属のコンシェルジュがあなたの要望に合ったIFAを無料で紹介。IFAとの相談料も無料ですから、気になった方は活用してみてくださいね。

つみたてNISAは投資のための制度なので、必ず成功する(利益が出る)保証はありません。しかしどうせ始めるなら失敗は避けたいもの。ここではつみたてNISAでの成功を助ける3つの秘訣を紹介します。
①コストの低い投資信託に積み立てるべし!
②取り扱い商品数が多い金融機関で始めるべし!
③少額から積み立てを始めるべし!
つみたてNISAの対象商品である投資信託には「信託報酬」という手数料がかかります。信託報酬は投資信託の運営や管理にかかる費用で、運用期間が長いほど多く支払うことになります。よって、長い期間運用するつみたてNISAでは信託報酬の安さが商品選びのポイントとなります。
同じジャンルの商品で同じくらいのリターンが見込めるなら、信託報酬の安い商品を選ぶとよいでしょう。運用期間中のコストが抑えられて、結果的に手元に残るお金を増やせます。
つみたてNISAを始めるためには金融機関で専用口座(つみたてNISA口座)を開設する必要があります。金融機関は自由に選べますが、取り扱い商品数やラインナップは異なります。
つみたてNISAの金融機関は取り扱い商品数が多いところを選びましょう。商品数が多ければコストや運用成績を比較してよりよいものを選べるので、失敗する可能性を減らせます。
つみたてNISA口座は1人につき1口座しか開設できません。年単位で金融機関を変えることはできますが、複数のNISA口座を管理しなければいけないデメリットが発生する場合もあります。そのためつみたてNISAを始める際の金融機関選びは非常に大切です。
商品数で業界トップクラスなのはSBI証券・松井証券・楽天証券などです。以下の記事で詳しく解説していますので、金融機関選びの参考にしてみてくださいね。
合わせてこちらもチェック!
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円(月3万3333円)までですが、最初からその金額で始める必要はありません。ご自身の収入や家計の状況を考慮して無理のない金額で始めることをおすすめします。
少ない金額なら損失が出たとしても限定的なので、初心者でも始めやすいでしょう。積立額はあとから変更することもできます。余裕が出てきたら徐々に金額を増やしていくとよいでしょう。
なお、先ほどご紹介したSBI証券・松井証券・楽天証券は月に100円から積み立てができますから、初心者にもおすすめのつみたてNISA口座の開設先と言えそうです。
つみたてNISAは長期の積立投資を支援するための制度です。そのため短期で利益を得ようとしたり、資金に余裕がないうちから始めたりするのは失敗のモト。そのような人はやめたほうがいいでしょう。どんなお得な制度でも、目的から外れた使い方をしてはメリットが得られません。
逆にある程度の貯蓄があり、そのうえで長期的に資産運用したい人には向いている制度です。住宅購入資金やマイホーム資金などご自身のライフスタイルに合わせて計画的に積み立てましょう。
つみたてNISAを利用するにあたって、注意点はありますか?
つみたてNISAでは損益通算や損失の繰越控除が受けられない点は注意が必要です。
損益通算とは複数の口座を持っている場合に、ある口座で出た損失と別の口座で出た利益を相殺する仕組みです。損失の繰越控除とは、損益通算したあとも損失が残る場合に、その損失を繰り越して翌年以降の利益から差し引ける仕組みです。
またつみたてNISAではロールオーバーができないことも覚えておきましょう。ロールオーバーは一般NISAとジュニアNISAに限定された制度で、5年の非課税期間が終わったあとに翌年の新たな非課税枠に移管することで非課税期間を延長できる制度です。つみたてNISAにロールオーバーはなく、非課税期間の延長はできません。
合わせてこちらもチェック!
いざ、NISAを始めよう!と思っても、数ある金融機関の中からどこを選べばよいか迷いますよね。そこで、多くの人に支持されている金融機関を、独自のサービスやおすすめ情報と併せてご紹介します。
SBI証券
松井証券
auカブコム証券
楽天証券
\ この記事をシェアしよう /

つみたてNISA(積立NISA)をやめたほうがいい人が持つ4つの特徴とは?

・当サイトの掲載情報は執筆者の見解であり、あくまでも参考情報の提供を目的としたものです。
最終的な投資決定は、各取扱金融機関のサイト・配布物にてご確認いただき、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
・当サイトの掲載情報は、信頼できると判断した情報源から入手した資料作成基準日における情報を基に作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。また、将来的な予想が含まれている場合がありますが、成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当サイトは、掲載情報の利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。
・当サイトの掲載情報は、各国の著作権法、各種条約およびその他の法律で保護されております。
・当サイトへのリンクは原則として自由ですが、掲載情報を営利目的で使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等)する事は禁止します。
