※このページはプロモーションを含みます
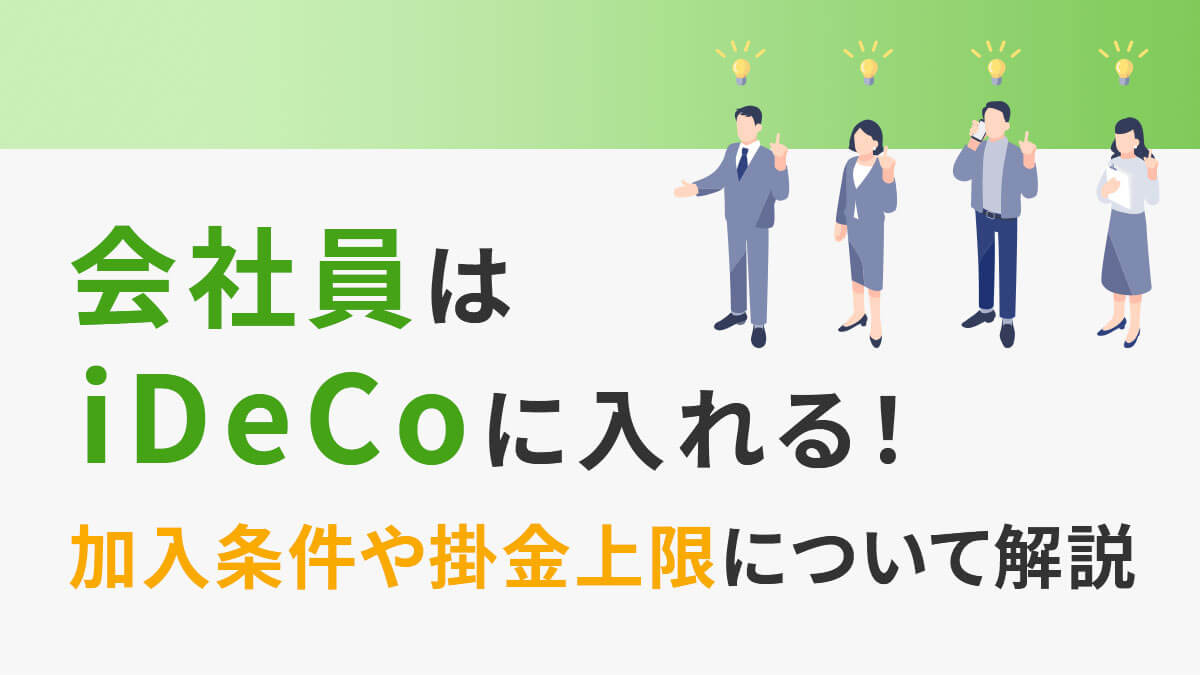
この記事は7分で読めます
iDeCo(個人型確定拠出年金、イデコ)は、2022年10月から要件が緩和され、企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)に加入する会社員でも、一部のケースを除きiDeCoに同時加入できるようになりました。
この記事では、会社員のiDeCoの加入条件、掛金上限、メリットなどを詳しく解説します。
目次
会社員でも基本的にiDeCo(イデコ)に加入できますが、企業型DCにも加入している会社員は、下表のとおり一部例外があります。
| 企業型DC | iDeCoの 加入 |
||
|---|---|---|---|
| マッチング 拠出※ |
選択していない | 〇 | |
| 選択している | × | ||
| 会社が拠出する掛金 | 各月の 限度額 |
超えない | 〇 |
| 超える | × | ||
| 各月拠出 | である | 〇 | |
| でない | × | ||
DCとは確定拠出年金のことで、企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)は掛金を支払う者が違います(企業型は会社が支払う、個人型は自分が支払う)。
企業型DCでマッチング拠出をしている人はすでに自分で掛金を上乗せしているため、個人型(iDeCo)との併用はできません。
そのほか、会社が拠出する掛金が各月拠出でかつ各月の上限(5.5万円)を超えないことが企業型DCに加入する会社員のiDeCo加入条件です。
iDeCoの毎月の積立金額(掛金)には上限があります。会社員は勤務先で加入している企業年金制度によって、下表のとおり上限額が異なります。
| 企業年金制度 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|
| 企業年金なし | 2.3万円 | 27.6万円 |
| 企業型DCのみ加入 | 2万円※1 | ※1×12カ月 |
| 企業型DCとDB※3に 加入 |
1.2万円※2 | ※2×12カ月 |
| DB※3のみに加入 | 1.2万円 | 14.4万円 |
会社員がiDeCoを活用すると、どんなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは以下の4つです。一つずつ分かりやすく解説していきます。
メリット1:
基本ほったらかしでOK!楽に資産運用ができる
メリット2:
積立したお金(掛金)が全額所得控除になる!
メリット3:
投資信託への積立で得た利益に税金がかからない!
メリット4:
受取時にも税負担を軽減できる!
iDeCoは毎月の掛金額と積立する商品を決めたら、あとは毎月自動で運用できます。
iDeCoの投資商品は主に投資信託です。投資信託とは、投資家から集めたお金を1つにまとめて専門家が運用し、利益を分配する金融商品です。投資信託では株式などの資産の売買は専門家が行うため、日々の株価などを自分で毎日チェックする必要はありません。
資産運用は難しいイメージがあるかもしれませんが、iDeCoなら基本ほったらかしでよいのはうれしいメリットでしょう。
iDeCoで積立したお金はその年の所得から全額控除(所得控除)できます。そのため課税される所得を少なくすることができ、所得税と住民税の負担を減らすことができます。
| 課税所得 | 税率(%) | 節税額(年間掛金ごと) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 14万4000円の場合 | 27万6000円の場合 | |
| ~195万円未満 | 5 | 10 | 21,600 | 41,400 |
| 195万円~ 330万円未満 |
10 | 28,800 | 55.200 | |
| 330万円~ 695万円未満 |
20 | 43,200 | 82,800 | |
| 695万円~ 900万円未満 |
23 | 47,520 | 91,080 | |
| 900万円~1800万円未満 | 33 | 61,920 | 118,680 | |
| 1800万円~4000万円未満 | 40 | 72,000 | 138,000 | |
| 4000万円以上 | 45 | 79,200 | 151,800 | |
例えば、課税所得(収入から給与所得控除額などを引いたもの)が、500万円の人の場合、所得税率20%、住民税率10%の合計30%の税金がかかります。
もし年間14万4000円(DBのみ加入者)の掛金を拠出すると、所得税・住民税を合計4万3200円(14万4000×30%)節税でき、年間27万6000円(企業型年金なし)の掛金を拠出すると合計で8万2800円(27万6000円×30%)節税できます。
掛金の拠出が多いほど、また課税所得が高く(税率が高く)なるほど、iDeCoの節税効果は大きくなります。
iDeCoでは預金・保険・投資信託に積立をすることができます。
通常、投資から得た利益には約20%の税金がかかります。しかし、iDeCoでは運用益が非課税になるのでこの税金がゼロになるメリットがあります。つまり、利益が出ても税金がかからず、丸々手元に残すことができるのです。
仮に投資信託で10万円の利益が出た場合、通常の投資とiDeCoを利用しての投資を比較して手元に残るお金にはどのくらい差があるのか、具体的に見ていきましょう。
| 通常の投資 | iDeCoの投資 | |
|---|---|---|
| 投資信託の利益 | 10万円 | 10万円 |
| 利益にかかる税金 (税率20.315%) |
2万315円 | 0円(非課税) |
| 税引き後利益 (手元に残るお金) |
7万9685円 | 10万円 |
10万円の利益に対して、iDeCoの投資では通常の投資と比べて手元に残るお金は2万315円多くなることがわかります。投資から得られる利益が大きくなるほど、iDeCoの節税効果は高くなります。
iDeCoで積立したお金は原則60歳以降に受け取ることができ、受取時にも税金の負担を減らす仕組み(受取金額からの各種控除)があります。
ただし上記控除は、それぞれ退職金や公的年金の受取時に同じ控除枠を使います。そのため、これらと合わせてiDeCoのお金を受け取ると、控除額を超える部分は非課税になりません。
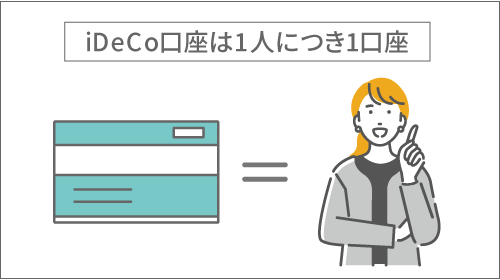
iDeCo(イデコ)口座は1人につき1口座しか持つことができません。また、金融機関は自分で選択する必要があります。
では会社員がiDeCoを始める場合、どんな金融機関を選べばいいのでしょうか。
iDeCoは、金融機関ごとに取扱商品・口座管理手数料が大きく異なります。取扱商品数が少ないと投資の自由度は低くなります。また、毎月の口座管理手数料が高いと、その分受取金額が減り投資効率が悪くなります。
そこで、取扱商品数が豊富で口座管理手数料が最安な金融機関を選ぶべきでしょう。
金融機関の口座管理手数料は、月171円が最安水準です。これらをふまえて、会社員におすすめのiDeCoの金融機関を3社紹介します。
| 口座管理手数料 | 月171円※1 | |
|---|---|---|
| 取扱商品数 | 計38本 | |
| 内訳 | 投資信託 | 37本 |
| 預金・保険 | 1本 | |
取扱商品は、元本確保型の預金が1本、投資信託(元本変動型)が37本と豊富です。
インデックス・ファンド(株価指数などの指標に連動した運用を目指す投資信託)は、手数料の安い「eMAXIS Slim」などのシリーズが、アクティブ・ファンド(指標を上回る運用を目指す投資信託)は、「ひふみ」などの人気シリーズを取りそろえています。投資対象は多岐にわたり、さまざまな投資家ニーズに対応できるでしょう。
| 口座管理手数料 | 月171円※1 | |
|---|---|---|
| 取扱商品数 | 計32本 | |
| 内訳 | 投資信託 | 31本 |
| 預金・保険 | 1本 | |
取扱商品は、元本確保型の預金が1本、投資信託(元本変動型)が31本と豊富です。
インデックス・ファンドは、「たわらノーロード」や「楽天インデックス・ファンド」などの人気シリーズがあるので投資初心者でも安心です。
| 口座管理手数料 | 月171円※1 | |
|---|---|---|
| 取扱商品数 | 計40本 | |
| 内訳 | 投資信託 | 39本 |
| 預金・保険 | 1本 | |
取扱商品は、元本確保型の預金が1本、投資信託(元本変動型)が39本と豊富です。
手数料の安いeMAXIS Slim、たわらノーロードなどのインデックスファンドシリーズがあります。ターゲットイヤーファンドの数が多いため、自分に合うターゲットイヤーファンドを見つけたい人にも適した金融機関でしょう。
iDeCoを始めるまでのおおまかな流れは以下のとおりです。基本的に書類のやりとりで手続きを進めていきます。
まずは金融機関でiDeCo口座を開設する必要があります。金融機関は自由に選べますが、国民年金基金連合会が口座振替契約を行っていない金融機関(外国籍の銀行等)は指定できません。
金融機関が決定したら、ネット等で資料請求を行い申込書類などを取り寄せます。
会社員が提出する書類は主に以下の2種類。取り寄せた書類に含まれているか、また申出書が「第2号被保険者用」となっていることも必ず確認しましょう。
書類作成では、捺印(金融機関届け出印)は認印でもOKですが、シャチハタネームは不可。また、書類に明記する基礎年金番号は、年金手帳やねんきん定期便で確認できます。年金手帳は会社が預かっているケースが多いので、勤務先の総務・人事担当に問い合わせて、取り寄せて確認するとよいでしょう。
ほかに、金融機関によっては運転免許証や健康保険証のコピー、住民票の写しや印鑑登録証明書などが必要な場合があります。事前に金融機関に問い合わせしておくといいでしょう。
なお会社員の方がiDeCoに加入するには、(2)について勤務先で書類を記入、作成してもらう必要があることも覚えておきましょう。
合わせてこちらもチェック!
会社員のiDeCoの掛金上限額は、勤め先に企業年金があるか否か、ある場合はその種類によって変わります。そのため、転職などで会社の企業年金制度が変わると掛金の上限額も変わることがあります。
iDeCoの受取時には一定額まで税金の控除がありますが、この控除額は退職金や公的年金の受取時にも適用されます。会社員は退職金や公的年金が比較的多いため、iDeCoの受取金を合算すると控除額を上回ることがあり、上回った金額には課税されます。
確定拠出年金の個人型(iDeCo)と企業型の違いは下表のとおりです。
| iDeCo(会社員の場合) | 企業型DC | |
|---|---|---|
| 加入者 | 厚生年金の被保険者(65歳以上は老齢年金の受給権のない人) | 企業型DC導入企業の勤務者原則70歳未満 |
| 加入手続き・ 運用商品の選択 |
加入者が選択した金融機関で行う | 会社が選択した金融機関で行う |
| 運用にかかる費用 (手数料等) |
個人負担 | 会社負担 |
| 掛金を拠出する人 | 加入者 | 会社(マッチング拠出は加入者) |
| 掛金上限 (月額)※1 |
12,000円~ 23,000円 |
27,500円~ 55,000円 |
| 掛金の税制優遇 (所得控除) |
全額対象 | 会社掛金は対象外(会社は非課税)マッチング拠出は全額対象 |
マッチング拠出ができる人でiDeCoと迷う場合は、次の点を比較して自分に合う方を選ぶと良いでしょう。
合わせてこちらもチェック!
会社の企業年金制度によって掛金の上限額は異なりますが、会社員でもiDeCoに加入することができます。ただし、企業型DCでマッチング拠出を選んだ会社員はiDeCoとの併用はできません。
iDeCoの魅力は、3つのタイミングで税制優遇があることです。
原則60歳まで引き出せないこと、受取時は必ずしも全額が非課税にならないことに注意をしながら、iDeCoを資産形成の一助としてみてはいかがでしょうか。
会社に知られずにiDeCoを始めることはできる?
現時点では、会社に知られずにiDeCoを始めることはできません
会社員がiDeCoに加入するには、「事業主の証明書」を会社に記入してもらう必要があるからです。
なお2024年12月以降は、企業型年金の情報がiDeCoを管轄する国民年金基金連合会へ提供されるようになり、会社員でも事業主の証明書を提出せずにiDeCoに加入できるようになる見込みです。
会社を辞めて無職になったらどうすればいい?
掛金の減額や積立を中断することができます
掛金を減額する、または中断して運用指図者になる、どちらかの対応ができます。
しかし、iDeCoの脱退や既にiDeCoへ拠出したお金を途中で引き出すことは基本的にできないので、原則60歳まで運用を続けなければなりません。
掛金を拠出しなくても口座管理手数料はかかるので、手数料負けしないように運用していきましょう。
iDeCo(イデコ)は一人一口座しか持てないため口座選びが重要。でも、多くの金融機関の中からどこを選べばよいか迷いますよね。そこで、分かりやすい基準として、iDeCo専門サイトNo.1の「iDeCoナビ」でよく見られている金融機関と、独自サービスがある注目の金融機関をご紹介します。
SBI証券
楽天証券
松井証券
りそな銀行
\ この記事をシェアしよう /

会社員はiDeCo(イデコ)に入れる!加入条件や掛金上限について解説

・当サイトの掲載情報は執筆者の見解であり、あくまでも参考情報の提供を目的としたものです。
最終的な投資決定は、各取扱金融機関のサイト・配布物にてご確認いただき、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
・当サイトの掲載情報は、信頼できると判断した情報源から入手した資料作成基準日における情報を基に作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。また、将来的な予想が含まれている場合がありますが、成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当サイトは、掲載情報の利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。
・当サイトの掲載情報は、各国の著作権法、各種条約およびその他の法律で保護されております。
・当サイトへのリンクは原則として自由ですが、掲載情報を営利目的で使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等)する事は禁止します。
